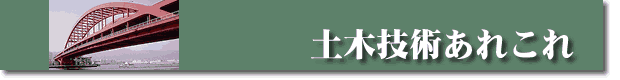丸木橋から超長大橋ヘ
原子力潜水艦の救助と海底工事
伊能忠敬と全国地図
丸木橋から超長大橋ヘ
動物達が歩いて出きる「けもの道」(しし(鹿路)道ともいわれます。)は、本能的に危険のない歩き易いところを選ぶので、安全であり、多くのけものが同じ所を繰返し歩くために通路として自然に出来あがってくるものであるということは、容易に想像できます。
川があれば浅瀬を探すか水面から顔を出している石伝いに渡るのが普通ですが、深い谷間を渡るには谷底への上り下りが加わるだけに深ければ大変な行程になります。このようなときに、たまたま倒木が架かっていればその上をたどることで容易に谷を渡ることが出来ます。一度や二度の経験では、意識的に倒木を探し出したり,切り倒して架けるところまではいかないでしょうが、長い年月の間には、架けたいところに架けることが出来るような知識を持った者が現れたと思われます。これが丸木橋の始まりと言えるでしょう。その後、さらに安心して渡れるように手すりなども付けられたり、何本かを並べて幅を広くしたりと徐々に進化したのではないかと考えられます。北海道などの寒冷地では、川の水が凍結するころ、氷の上に板や柴を敷き並べて、これらに毎晩水を掛けて氷を厚くして人馬が通れるようにした「氷橋」も造られていたようです。
このような生活上の変化は、数多く放映されている熱帯地帯のジャングルや開発の進んでいない山岳地帯、草原などに住んでいる人達の自然のままの日常生活を克明に撮影し、紹介するテレビ番組を見ていると、水場や農地までの道路ともいえないような踏み分け道のあり様や濁流を苦労して渡っている様子などから、橋と人類の生活との関わりの変遷や社会基盤整備の歴史を知ることが出来ます。
ヨーロッパと異なって、わが国では、明治時代以前の橋のほとんどが木で作られていました。これらの沢山ある木の橋の中で、山梨県大月市の山間の渓流に架けられている「猿橋」及び山口県岩国市にある「錦帯橋」と、現在は、既に無くなっていますが、長野県木曾郡の「桟橋(かけはし)」が特殊な構造であることから「日本の三奇橋」と言われています。この中の錦帯橋は、1673年に架けら、翌年流出しましたが、直ぐに架け替えられ、その後何度かの補修はありますが、279年間流されも壊されもせず、1950年の台風による洪水で流出するまで架かっていました。
石造りのアーチ橋は、わが国では、1600年代に九州地方で架けられようになりましたが、ヨーロッパでは、紀元前から架けられ、16世紀の終わり頃までは、石造りのアーチ橋が多用されていたようです。
外国では、17世紀初頭になってから、鉄などを用いた橋が架けられるようになってきました。1820年になって、錬鉄製アイバー・チェンを使用したスパン137mの当時世界最長のユニオン吊橋が架けられました。その後、1841年にアメリカで平行線ワイヤ・ケーブルが開発されるまでの初期の吊橋では、色々な事故が多発したようです。また、この頃から各種のトラスの特許が取得されていますし、色々な種類の形式や材料を用いた橋も架けられるようになっていました。
吊橋の長大化は、1937年に完成した中央支間1280mのゴールデンゲート橋が切っ掛けになりました。わが国の本格的な吊橋は、1962年、北九州市の洞海湾に架けられた中央支間367mの若戸大橋とそれに続く中央支間712mの関門大橋から本州四国連絡橋を経て、現在世界最長の中央支間1991mの明石海峡大橋へと発展してきました。
「本州北海道架橋を考える会」(http://www.kh.rim.or.jp/~hhbridge/)等が提唱している本州大間町と北海道戸井町間の約19kmの津軽海峡を跨ぐ夢の架け橋「津軽海峡大橋」は、中央支間が、3、000〜5,000mの吊橋が何橋か連なったものになるものと思われますが、このような超々長大橋を実現するためには、明石海峡大橋に用いられたものより軽くて高強度のケーブルの製作、冬期間に長時間吹く強い北西の季節風に対する対策、水深200mの地点に設置する橋脚や橋台の工法など色々な新しい技術を開発する必要があります。このように「津軽海峡大橋」が夢ではなくなるまでにはまだ相当の年月が必要ですが、長い調査期間を経て工事に掛かるまでには、これらの技術的問題は、全て解決でき、夢が実現できるものと確信して「本州北海道架橋を考える会」は、地道な活動をしています。
原子力潜水艦の救助と海底工事
少し古い話になりますが、118人が乗り組んだロシアの原子力潜水艦「クルスク」が、北極圏のバレンツ海の水深108m地点に沈没したと報道されたのは、2000年8月16日のことでした。現在の技術レベルであれば容易に救助できるのではないかと予想していました。しかし、ロシア海軍は、自国の最新機種の小型潜水艇を使って救助しようとしましたが、潜水艦が傾いて着底していることと強い潮流に阻まれて作業が難航したようでした。ロシア海軍としては,軍事機密保持の観点から、あくまでも自力で救出することにこだわっていたようですが,思うように作業が進まないこともあって、その後、イギリスとノルウエー海軍の協力を得て救助に当りました。
このときのノルウエー海軍の装備が新聞紙上に紹介されていました。海上の母船から空気や電気が供給され、通信ケーブルの繋がった潜水鐘(お寺の鐘の大きな形のもの)に12名のダイバーが乗込んで、体を深海の水圧に対応できるようにしながら海底近くで待機し、3名ずつが交代で潜水鐘から出て作業をする方式です。水深10mで1気圧増えますから11気圧前後の強い圧力を受けることになります。また、水温も0〜4℃ですので、普通の空気ではなく、温められたヘリウムガスと酸素の混合ガスの供給を受けることができ、温水が循環する特殊な潜水服を着用して、作業用の照明とカメラで作業状況を記録しながら救助作業を行ないました。母船では、遠隔操作のカメラで作業状況を監視し、作業の指示と安全確認をしていたようでした。この報道から判断しますと、ロシア海軍の技術ては、この水深になると人間が直接海中で作業を行なうことが出来ないことを示しています。
津軽海峡に橋を架ける際に、国際海峡ということもあって、海峡中央部の吊橋の中央径間は、3,000mを越え、橋脚の設置地点は、水深が200〜250mになると考えられています。わが国で既に実績のある橋脚設置地点の水深は、明石海峡大橋の50m程度ですから、現在の日本の潜水技術では、施工が不可能ということになります。しかし、正確なことは判りませんが、アメリカ海軍には、このような水深が200〜250mの深海に潜水できる技術があるといわれていますので、日本の海上自衛隊にもかなりの水深までの潜水技術があるのではないかとも予想できます。
津軽海峡大橋を実現するためには、このような深海海底における施工技術の開発と実地訓練を継続することも必要になりますし、人が潜水しなくても橋脚の据付工事が出来るような技術を開発することも考えなければなりません。明石海峡大橋の完成と共に、長大橋の架橋工事が途絶えそうな気配もありますが、現在の高度な技術の維持とさらなる発展のためにも、あまり間を空けずに、現在検討されている紀淡海峡、豊予海峡、東京湾口、伊勢湾口、島原〜天草〜長島間などの工事が順次実施されることを望んでいます。
津軽海峡に横断橋を架けるためには、この他にも解決しなければならないことが沢山ありますが、技術者達にとっては、おおいに挑戦意欲をかき立てられる問題ですので、嬉々としてこれらの問題の解決に立ち向かっています。この架橋構想が具体化するまでには、各種調査に最低でも10〜30年程度の期間が必要でしょうから、その間にこれらの技術的な障害は、全て解決されて存在しなくなっているものと予想しています。
1日も早く、本州下北半島の大間町と北海道戸井町の汐首岬の間に架けられた雄大な橋の全景を函館山の頂の展望台から眺めることができることを夢見ています。
伊能忠敬と全国地図
当時としては極めて高齢の55歳になった伊能忠敬が71歳までの17年間に渉って、全国各地を測量し、明治時代になってヨーロッパの技術による測量が行われるまで使用された大日本沿海輿地全図を完成させたことは良く知られています。しかし、この測量の最初のスタート地点が函館であることを函館の人でも知らない人が多いようです。
伊能忠敬が全国地図の作成を始めた切っ掛けは、緯度1度の距離を正確に測定し、地球の大きさを定めることで暦学者としての功名心を満足することにあったようです。正確に距離の判っている南北の2点で、北極星に対する角度を測定すると緯度1度の距離を計算で求めることができます。この2点間の距離は長いほど良いわけですが、測量で1番難しいのが正確な距離の測定です。特にこの時代には、間縄と言うテープに相当するものはありましたが、両端の引っ張り方による伸び縮みの問題があり、あまり正確ではなかったようです。伊能忠敬は、常に2歩で1間(約1.8m)となるように歩く訓練をして、歩数によって距離を測定しました。伊能忠敬の生涯を描いた井上ひさしさんの「四千万歩の男」と言う小説の題名はこの事実から来ています。身長によって異なりますが一般的な歩幅は、60〜70cm程度ですので、90cmの歩幅で歩く様は、異様な感じを与えたのではないかと思われます。小説の中で、剣術の達人と誤解されるところがありますが、腰の高さが常に一定でなければこのような歩き方ができません。これが剣術の極意に通じるために、そのように思われることがあったのではないでしょうか。
このときの北海道の測量は、函館の蝦夷掛役所に出頭してから実施しています。5月29日に函館を出発し、現在の大野町、森町鷲の木を経て、海岸に沿って歩けないときは山側を、それ以外のときは太平洋岸に沿って、距離は歩数、角度はコンパスによって測定する現在のトラバース測量による実測と天体測量を実施し、70日ほどの日数を掛けて8月7日に根室の別海町に達しています。
この「奥州街道蝦夷地南東岸測量行」は、全長3224.89kmを180日掛けて歩いて、寛政12年10月21日(1800年12月7日)に江戸に着いています。その後、二月ほどを掛けて、縮尺が1/43636の大図12枚と1/436360の小図を作成し、提出しています。これが「大日本沿海輿地全図」225枚を完成させる最初の地図ということになります。
このページのトップに戻る